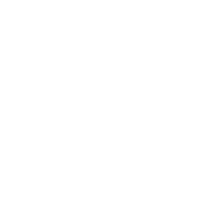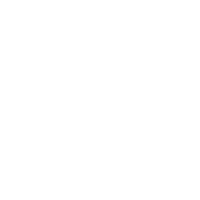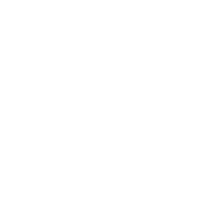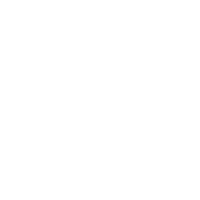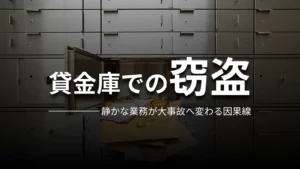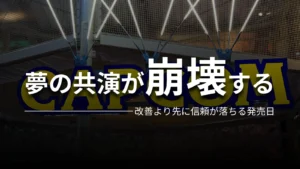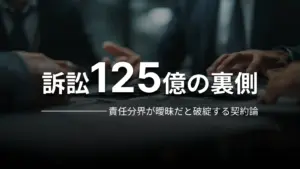東京五輪入札談合の代償と教訓 | 電通の失敗と再起の道筋

会議室の静けさは、外の喧騒よりも重かった。競争の設計を生業とする私たちが、競争そのものを歪めたと指摘されたとき、言葉は役に立たない。資料は揃い、証言は積み上がる。だが本当に問われているのは、何をしたかではなく、なぜそうなったかだ。商機の熱狂、慣行の惰性、成功体験の呪縛。幾つもの因子が絡み合い、判断は鈍り、線は滲む。やがて行政の結論は下り、私たちは向き合う。過去ではなく、これからの行動に。責任の取り方は一つではないが、再発を許さない選択は一つだ。この物語は、規模でも肩書でもなく、意思決定の質が企業を左右するという単純で厳しい真実を見せる。読後に残るのは、方法ではなく態度の輪郭である。
この物語の主役となる企業はどこか
これは、株式会社電通の物語。日本の広告市場で長く中心的な役割を担い、統合マーケティングからスポーツ・イベント運営まで幅広い領域を担ってきた企業だ。国内外のグループ会社とともに、クライアントの成長と生活者の体験を結び直すことを掲げ、巨大な案件を調整し、設計し、支える。東京2020大会でも、私たちは商業と文化の結節点に立っていた。だが、市場の期待と機会が重なる場面ほど、組織は思考停止に陥りやすい。本稿は、その緊張の中で起きた意思決定を、一つの出来事に絞って描く。起点は、入札談合の疑いから始まった一連の調査と処分、そしてその後の選択である。企業の名声と信頼が試された瞬間だ。
- 巨大案件での意思決定の盲点と、業界慣行や成功体験が判断を鈍らせる構造
- 行政処分への初期対応(受入/不服/訴訟)と、株主・顧客・行政に対する説明責任の設計
- 再発防止を“仕組み”に落とす体制、KPI、監督機能の配置と、風土改革を連動させる方法
- 事実認定と自社理解のズレを前提に、訴訟と信頼回復施策を同時進行させる実務の勘所
- 成果測定(外部評価・内部学び・顧客行動)を因果の見立てと併記する視点
どんな問題に直面していたのか
発端は、東京2020大会のテストイベント運営などを巡る入札談合の疑いだった。2022年11月25日、特捜部と公正取引委員会の合同捜索が入り、業界全体に緊張が走る[1]。調査は行政処分と刑事手続の両面で進み、やがて八社が関与したとする認定に至る[2]。案件規模が大きいほど、利害調整のための事前協議は増え、境界は曖昧になりがちだ。プロジェクト成功という大義と、競争確保という規範が衝突する場面で、現場は“慣行”に頼り、意思決定者はスピードを優先しやすい。市場から見える成果が大きいほど、プロセスの正しさを疑う視線は厳しくなる。行政の結論は、再発防止と説明責任の重さを企業に突き付けた。公正取引委員会は、排除措置命令と課徴金納付命令を出し、株式会社電通グループに4億9,556万円、株式会社電通に4億2,515万円の納付を命じた[3]。ブランド毀損、入札資格への影響、グループ全体の統治再設計といった副作用も現実化する。社内では事実認定と現場感のズレが生じやすく、説明の遅れは疑念を拡大する。利害関係者は株主、取引先に及ぶ。対応を誤れば、訴訟や取引制限の連鎖を招き、回復に年単位の時間が要る。
どうやって解決しようとしたのか
—ここから先は会員限定です—
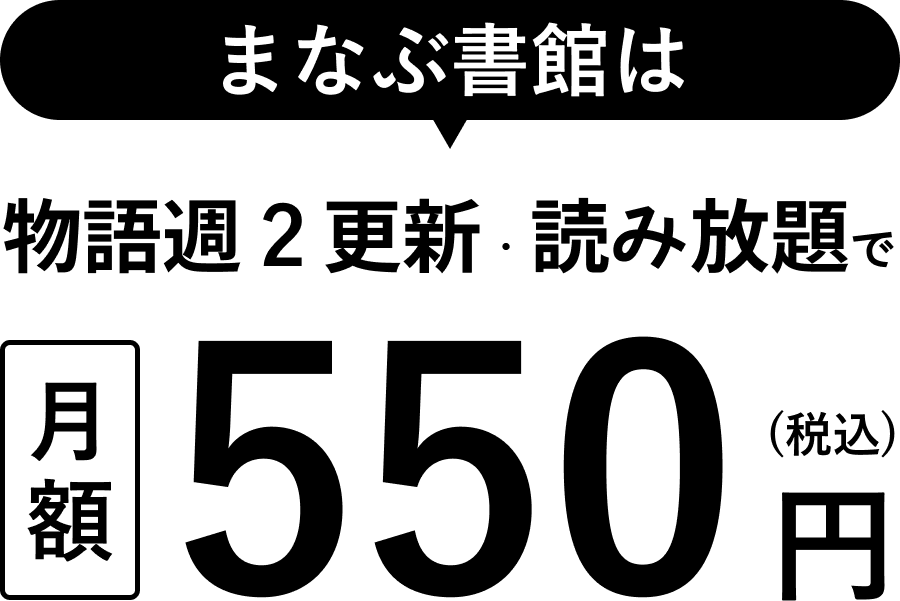
会員登録済みの方はこちら
- ステップ①
入札基準書・協働ガイドラインの制定→国内外への即時適用 - ステップ②
ケース研修・通報制度のKPI化→四半期レビューと改善サイクル - ステップ③
テーマ監査+突発監査→結果を報酬連動・ポータルでの可視化