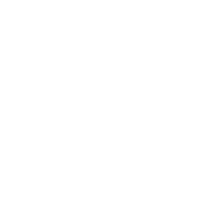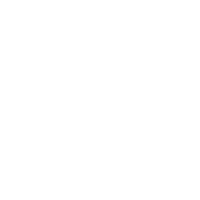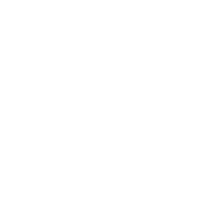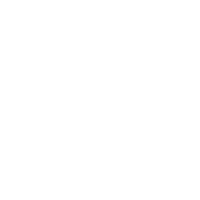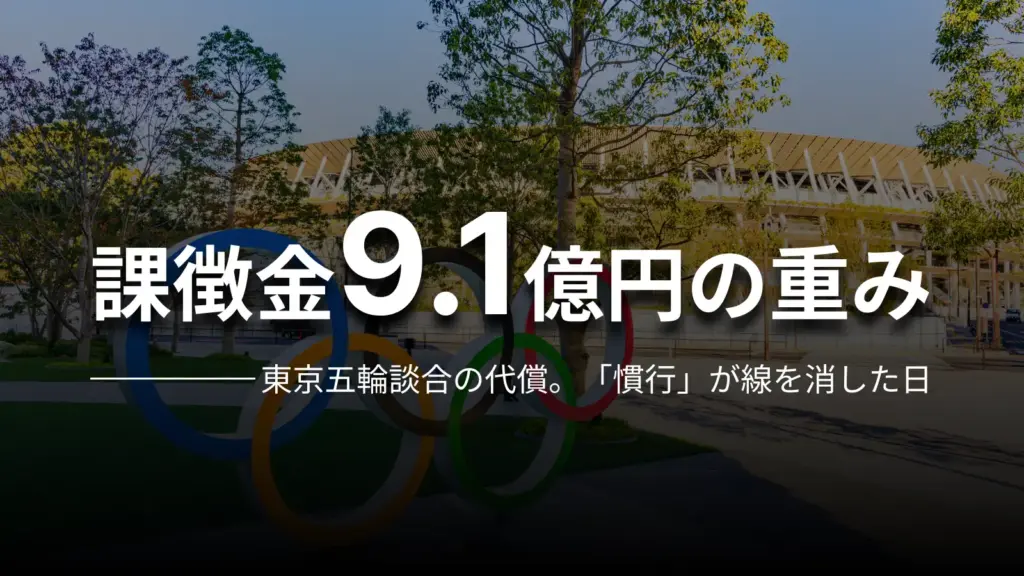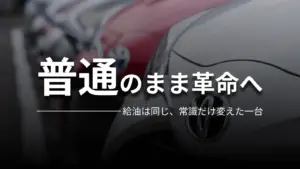ばらばらのAIを束ね、AIネイティブ化で成長を取り戻した日々

AIが流行語ではなく、経営の道具になった頃、現場には小さな成功が点在していた。自動でレポートがまとまる。広告配信が賢くなる。だが、成果は部門の机の上で止まりやすい。点が増えるほど、組織は迷う。どの部署が持つべきか、誰が責任を負うべきか。顧客も同じだった。部門ごとに導入したAIが、全社の価値につながらない。放置すれば、AIは“便利な小道具”のまま、競争力だけが静かに落ちていく。時間だけが過ぎ、判断の先送りが積み重なる。やがて、取り返しのつかない差になる。この物語は、その迷いを“仕組み”で断ち切ろうとした一手から始まる。AIを使う前に、AIを使いこなすための組織を先に作った。[1]
この物語の主役となる企業はどこか
これは、株式会社電通の物語。広告会社として知られながら、その仕事は「広告をつくる」だけでは終わらない。企業の成長戦略、顧客体験、データ活用、そして組織そのものの変革まで、頼まれる範囲は広い。多数の専門職が同じ案件を見つめ、クリエイティブとテクノロジーを同じ机の上で扱う。その構造は強みであり、ときに複雑さにもなる。2025年、国内電通グループはAI戦略「AI For Growth」を掲げ、実装の段階へ踏み出す。支援の対象は、マーケティングに留まらず、業務プロセス改革(BPR)まで伸びていく。千人規模の専門人財を束ね、顧客の変革に伴走する“中枢”を持った。[1][4]
- AI導入を“道具選び”から“運用設計”へ切り替え、責任・権限・判断基準・リスク許容を先に固定する
- 分散したデータ、人材、案件知を横串で束ね、部門の効率化を顧客体験と事業成長へつなげる翻訳者になり、社内の抵抗まで含めて設計する
- 外部パートナー連携では、技術導入と同時に人材育成・業務プロセス改革(BPR)・定着KPIを設計し、セキュリティや法務も巻き込み、短期と中期をそろえ迷いを減らすために
どんな問題に直面していたのか
顧客企業の会議室では、AIの話題が毎回のように出た。生成AIの実験が増え、部門ごとにツールが導入される。しかし、現場の改善は点で終わり、売上や顧客体験の変化として語れない。理由は単純だった。データの権限、セキュリティ、法務、業務プロセス──越えなければならない壁が、部門の外側にある。結果として「使える部署」だけが速くなり、会社全体は遅いまま残る。経営はAIの価値を測れず、投資判断も揺れる。導入が進むほど、ガバナンス不足は情報漏えいなどの事故リスクを増やし、スピードにブレーキをかける。顧客が欲しいのは、ツールの説明ではなく、成長の筋道だった。[4] 株式会社電通は、顧客の変革を支える立場でありながら、自らも分断と向き合う必要があった。案件ごとに最適解を出せても、それを横展開する仕組みがなければ、知見は散らばり、同じ学習を何度も繰り返す。さらに、AIの進化は速い。属人的な努力に頼れば、スピード勝負で負ける。点在する成功を束ねられなければ、AIは“投資”ではなく“コスト”に化ける。[4]
どうやって解決しようとしたのか
—ここから先は会員限定です—
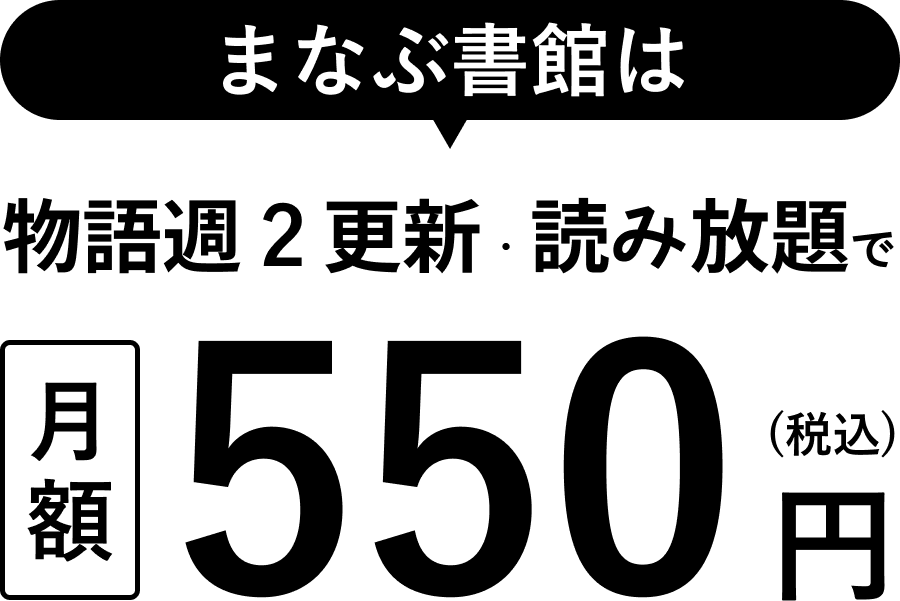
会員登録済みの方はこちら