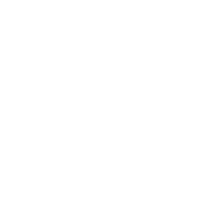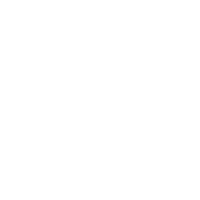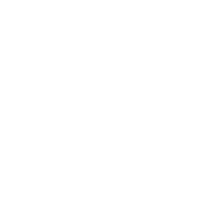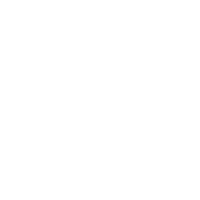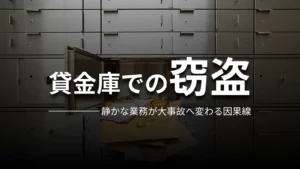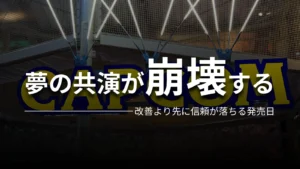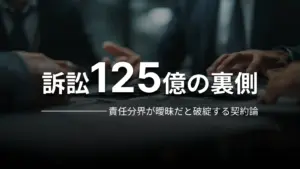勝ち続けた企業が法廷でつまずいた日、特許戦略が見落とした盲点

製造現場の「困った」を先回りし、世界初・業界初を連ねてきた会社がある。その名は、株式会社キーエンス。けれど物語の舞台は、工場ではなく法廷だ。光電センサをめぐる争いで、同社は「止めてほしい」と訴え、損害賠償も求めた。相手は静かに反撃し、特許の根っこを揺らしに来る。裁判所が見たのは、図面の細部だけではない。「その差は、本当に新しいのか」という問いが、冷たいライトの下で反復される。準備した言葉が一つずつ剥がれ、最後に残るのは“想定していなかった前提”だ。会社の時間も、評判も、少しずつ削られていく。結末は、痛いほど静かだ。 勝ち筋ほど、検証の省略を誘う。
この物語の主役となる企業はどこか
これは、株式会社キーエンスの物語。ファクトリー・オートメーション(FA)向けのセンサや測定・画像処理機器で、現場の課題を「商品」で解くことに執着してきた。付加価値の創造を企業の存在意義に据え、世の中になかった商品を届ける姿勢を明言する。[3] 新商品の約70%が世界初・業界初だと掲げるのも、その覚悟の表れだ。[4] だからこそ、模倣に敏感で、技術の差を知的財産で守ろうとする。その強さは、企画開発だけでなく、顧客に密着するダイレクトセールスにも支えられている。[3] 強さの源泉は“現場への近さ”だが、法廷では別の近さが問われた。
- 「守るための訴え」が逆に弱点を晒す瞬間を知る
- 決断前に、先行技術(過去に公開された技術)と制度リスクを洗い出し、勝てる条件を数行で言語化してから動く方法を学ぶ。これが意思決定の摩擦を減らす
- 負けた後でも、技術・営業・法務の連携を組み直し、顧客への説明、製品の差別化、知財の棚卸しを同時に回す道筋を掴む。小さな失点を次の強みに変える術を持つ。それが組織の学習速度を上げ続ける
どんな問題に直面していたのか
2000年代、FA用光電センサは改良の余地が大きい一方で、機構が見た目として似やすい領域でもあった。株式会社キーエンスは差別化の核を“機能の組み合わせ”に置き、電子機器ユニットの結線構造に関する特許(特許第3457107号)を盾にしようとした。[1] ところが競合のオプテックス・エフエー株式会社が、同種の構造を持つ製品を製造・販売しているとして争いが起きる。[1] 放置すれば、模倣の連鎖が起こり、営業が現場で語ってきた「違い」が、値引きの理由に変わってしまう。だから同社は、差止めと損害賠償(請求額4,500万円)を求めて提訴した。[1] だが、訴訟は一本道ではない。相手は無効審判を請求し、過去の公報を次々に並べ、進歩性(容易に思いつくかどうか)を争点に押し上げた。[1] 裁判所は特許法104条の3の枠組みで、権利行使を認めない可能性を検討し始める。[1] 外に出た争点は、技術者の机だけでは回収できない。法廷は、時間を食い、関係者を増やし、説明の粒度を上げる。技術を守るはずの場で、守れる前提そのものが揺れる。準備不足の影は、短期の勝ちを求めるほど濃くなる。 攻めの訴訟が、特許の耐久力テストになってしまった。
どうやって解決しようとしたのか
—ここから先は会員限定です—
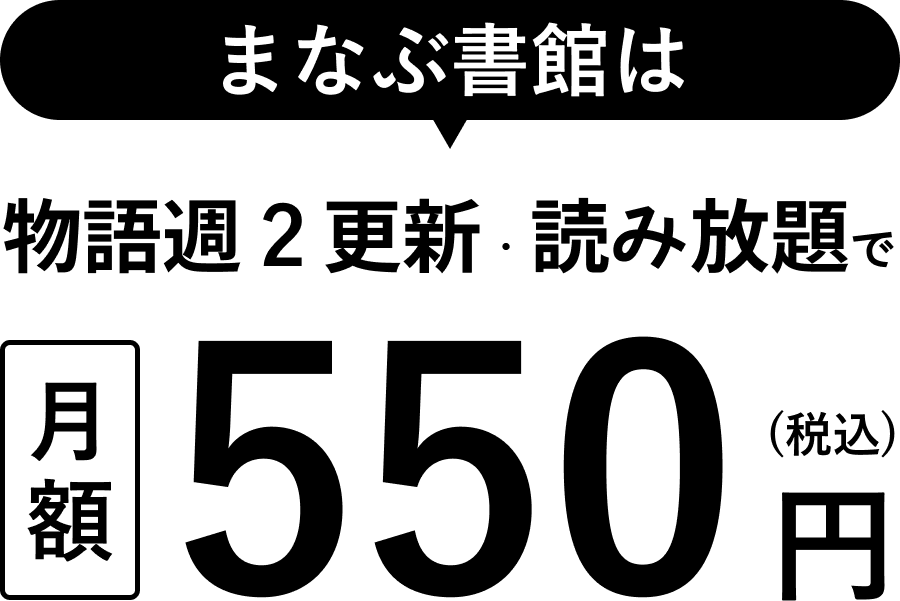
会員登録済みの方はこちら