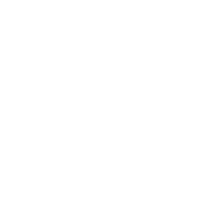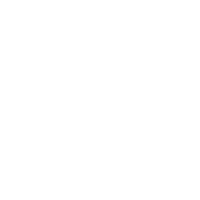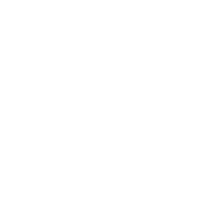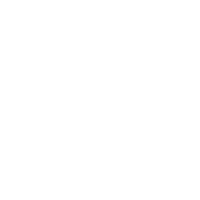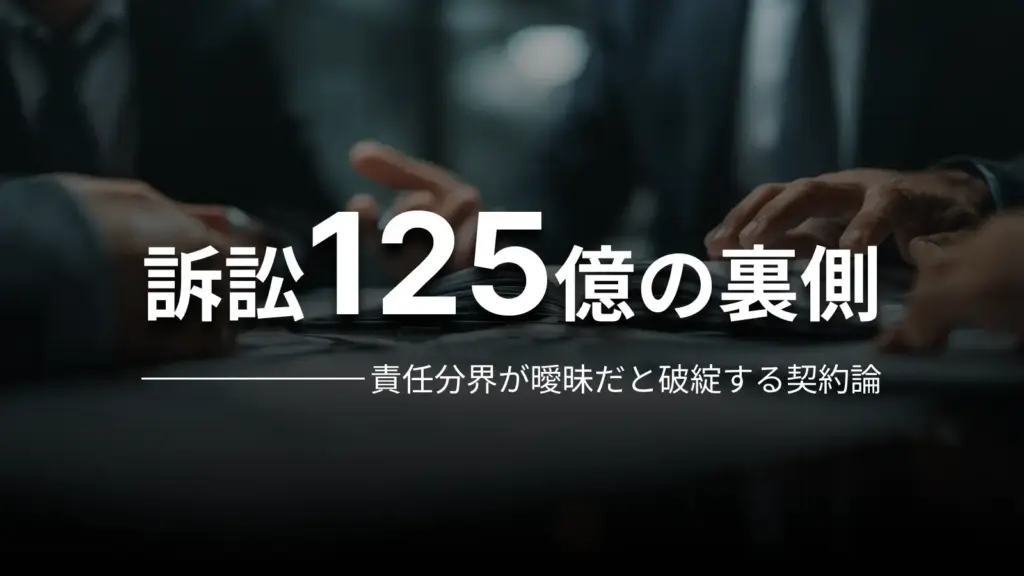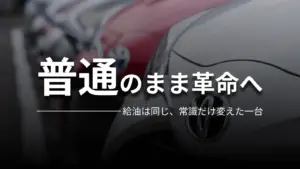3年30億ドルの賭けが、企業のAI導入を現場へ落とす

AIという言葉が空気のように漂い始めた頃、企業は皆、同じ不安を抱えていた。試したい。しかし、試すほどに責任とコストが膨らむ。そんな揺れる市場に、あるプロフェッショナル集団は“賭け”の額を公にした。3年で30億ドル。大げさに見えて、実は現場の小さな迷いを断ち切るための道具だった。その後、提携と人材の話が雪だるまのように増え、決算資料には生成AIの受注額が堂々と並ぶようになる。だが物語の起点は、派手なデモでも新製品でもない。会議室で交わされた「今、動くか」という一言だ。そして、その速度が、後の数字に姿を変える。投資の本当の狙いは、技術ではなく意思決定の速度を買うことだった。[1]
この物語の主役となる企業はどこか
これは、アクセンチュア株式会社の物語。企業の戦略からシステム、運用までをまたいで支援し、120カ国以上の顧客にサービスを届けるプロフェッショナル集団だ。社員は77万4,000人規模にのぼり、社内だけでも一つの社会のように大きい。[3] デジタル化の波は何度も来たが、生成AIは性質が違う。「便利な道具」で終わらず、働き方そのものを塗り替える。だからこそ主役は、自分たちの業務で先に試し、責任ある運用の型を作ってから顧客へ渡すという順序を選んだ。その選択は外からは地味に見えたが、あとで効いてくる。大企業ほど動けないという常識を、仕組みと人材でひっくり返すのが彼らの仕事だ。
- 大きな投資を「施策」ではなく、意思決定の型として設計し、現場の迷いを減らして進む基準を一本にし、流行に振り回されない
- 責任あるAI運用(倫理・ガバナンス)を先に固め、規制やセキュリティの不安を言語化して共有し、社内外の合意と責任の所在を速める
- PoC=概念実証で止めず、標準化した部品・提携・人材育成を束ね、受注で打ち手を整え、数字が鈍れば配分を変えて展開を着実に最後まで走り切る
どんな問題に直面していたのか
生成AIが爆発的に注目された一方で、企業の現場は冷えた算盤も抱えていた。学習データの扱い、著作権、個人情報、モデルの偏り。どれも「便利そう」の裏で、事故が起きた瞬間に信用が崩れる。さらに多くの企業は、AI以前にデータが散らばり、業務プロセスも部署ごとに違うままだった。AIを入れても、試験運用(PoC=概念実証)が増えるだけで、本番に移せない。顧客からは「どの業務で、いくら浮くのか」「責任ある運用指針は誰が持つのか」と問い詰められるが、答えは案件ごとに毎回作り直しになる。外では人材争奪が始まり、内ではコスト抑制の圧力が強い。支援側のアクセンチュア株式会社も例外ではなく、提供の型がなければ属人的に燃え尽きる危険があった。加えて、クラウドやソフトウェア企業がAIの“標準部品”を抱え始め、コンサルティングが上流だけで終われば価値が薄れる。放置すれば顧客は別の支援者へ流れ、逆に急げば炎上の責任が返ってくる。速さと安全の両立という矛盾を、解ける形にしなければならなかった。しかも期限も迫る。「とりあえず試す」を続ければ、時間と信頼だけが静かに溶けていく。[1]
どうやって解決しようとしたのか
—ここから先は会員限定です—
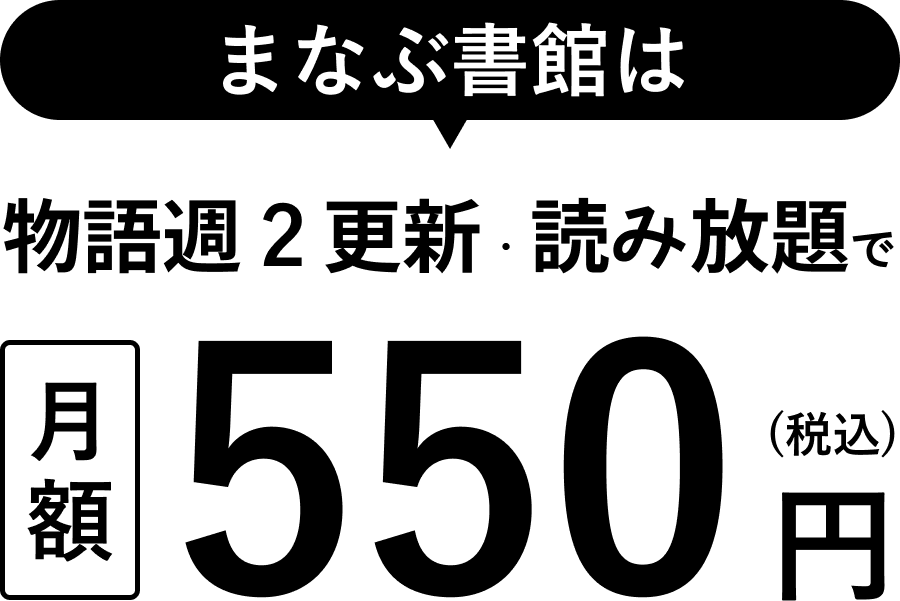
会員登録済みの方はこちら