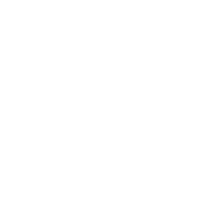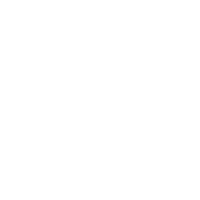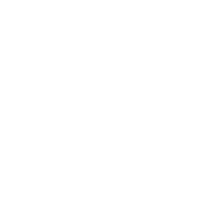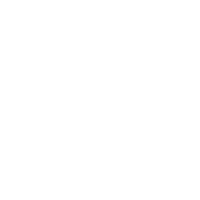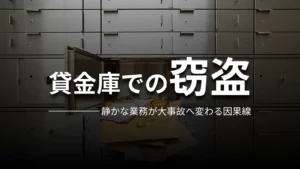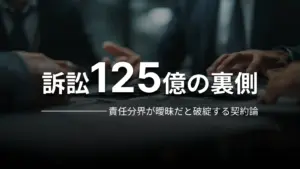夢の共演が冷えた日、初動設計が未来を決めた失敗

遠い世界の英雄たちが、同じ画面に立つ。そんな約束は、誰の心にも火を灯す。ところが火は、薪をくべなければ消える。『MARVEL VS. CAPCOM: INFINITE』は、夢の共演で始まり、冷えた空気の中で終わった。大きな看板は、勝利の近道にも見える。だがそれは同時に、期待の高さという重さでもある。市場は、最初の体験だけで判断を下す。そこに落ちた小さな影は、後から直すほど濃く見え、物語の筋書きを変えていく。
目次
この物語の主役となる企業はどこか
これは、株式会社カプコンの物語。大阪に根を張り、家庭用ゲームからアーケードまで、何度も時代をまたいできた。『バイオハザード』や『モンスターハンター』のように、自社で世界を作り、長く育てることに強みがある。熱量の高いファンが多く、シリーズの歴史も深い。だからこそ“格闘”という舞台は似合っていた。だが同時に、借りた旗の下で見せるものが、会社の顔になる。共演は追い風にもなるが、風向きが変わると、身を隠す場所がない。
何を学べるのか
- 期待値が高いほど、最初の体験設計が失点の倍率になる
- 「後から直す」運営設計は、初動の人口維持が条件になる
- 共同企画は制約が増えるほど、約束の粒度を小さくする必要がある
どんな問題に直面していたのか
株式会社カプコンは、格闘ゲームの時間の流れを知っていた。発売日に人が集まり、熱が生まれ、そこから大会や配信へ火が移る。熱が残れば、追加要素で長く育つ。だが熱が冷えれば、人口が減り、マッチングが崩れ、体験がさらに痩せる。しかも本作は、MARVELという巨大な期待を背負う共同企画だった。[1] 約束は大きくなる。表現の確認や調整も増える。納期は動かしづらい。完成度の不安が見えても、止めるほどの余裕はない。共同IPは追い風であるほど、同時に“足かせ”にもなりやすい。放置すれば、失望は拡散し、コミュニティは静かに離れ、長期運営の前提そのものが崩れる。時間は味方ではなかった。
どうやって解決しようとしたのか
---ここから先は会員限定です---
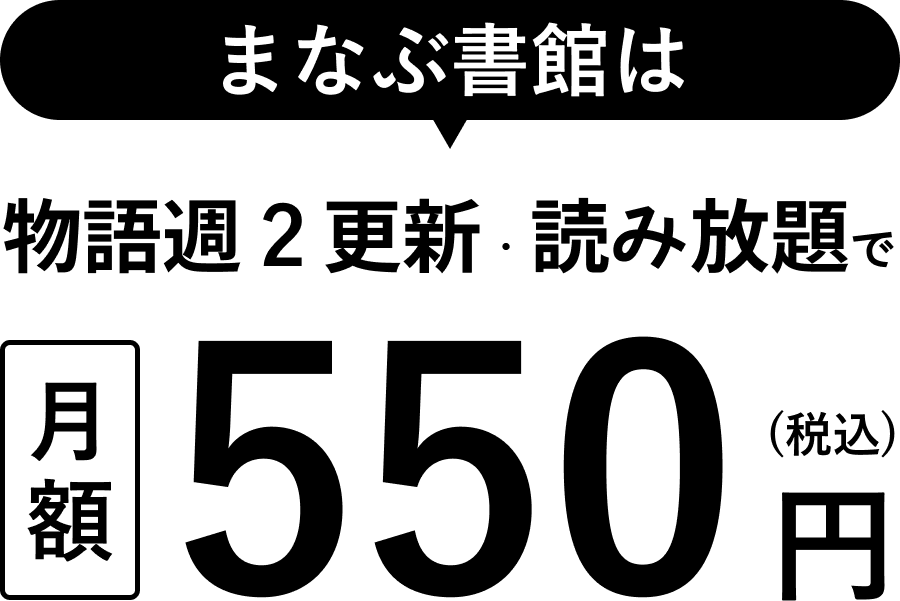
会員登録済みの方はこちら
カプコンの他の物語を読む