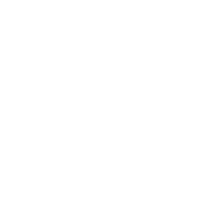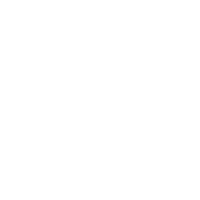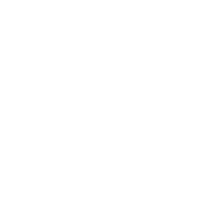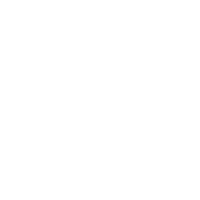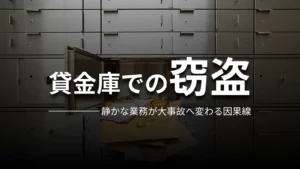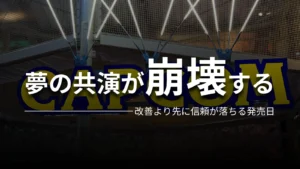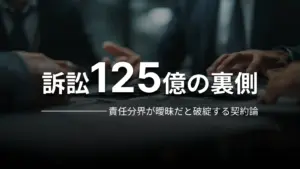東京ロボタクシー計画が止まった“前提崩壊”の夜明け

夜の東京は、いつもより少しだけ静かだった。計画書の上では、2026年初頭に無人のタクシーが都心を走る。[1]合弁会社を立ち上げ、運転席のない車両を並べ、アプリで呼ぶ。未来は手の届く距離に見えた。タクシー会社は停車場所を測り、自治体は道路の線を引き直し、現場は「乗せ方」を練りはじめる。だが、この物語は成功の凱歌ではない。外部の力で加速したはずの時計が、ある日ふいに止まる。止まったのは技術ではなく、前提だった。事故、規制、資本、そして信頼。準備が進むほど、説明の責任も増える。誰が安全を語り、誰が責任を負うのか。“できるか”ではなく、“続けられるか”が問われた瞬間、計画は別の顔を見せた。
この物語の主役となる企業はどこか
これは、本田技研工業株式会社の物語。二輪と四輪で世界の移動を支えてきた。エンジン中心の競争は、移動サービスの競争へゆっくり姿を変える。センサー、ソフトウェア、運行オペレーション、そして安全を証明する仕組みが、製品の外側に積み上がる。そこで本田技研工業株式会社は、自動運転企業クルーズ(Cruise LLC)と、ゼネラルモーターズ(General Motors、以下GM)と組み、都心での自動運転タクシーを構想した。[1]それは新規事業であると同時に、信頼を扱う試験だった。得意なものづくりを起点にしつつ、サービスの実装まで自社の責任として背負う覚悟が問われた。
- 前提が崩れた瞬間に止める基準を、最初に文章化する。そして撤退後に回収するデータと学びも同時に決める
- 協業でスピードを買うほど、規制当局や顧客に対する説明責任が誰に乗るかを、契約と運行体制で見える化し、月次会議で議事録化する
- 技術KPI(重要業績評価指標)だけでなく、遠隔介入回数や苦情率、安心感スコアなど“信頼KPI”を毎月更新し、判断を早める。属人性を減らし外部にも説明しやすくする
どんな問題に直面していたのか
自動運転タクシーは、車を作れば終わりではない。走る場所、停まる場所、緊急時の連絡、遠隔支援の手順、そして事故が起きた時の説明。それらは、道路という公共空間の上で初めて意味を持つ。本田技研工業株式会社が東京都心で描いた計画は、運転席のない専用車両を前提に、合弁会社を立ち上げてサービスとして提供するという挑戦だった。[1]背景には、都市の移動が高齢化と人手不足にさらされ、深夜や郊外ほど供給が細る現実がある。だが挑戦は、社内の技術課題だけではない。安全を語る言葉は、規制当局の期待、世論の温度、海外での実績に左右される。協業でスピードを買うほど、その実績が揺れた時の衝撃は大きい。また、運転席のない車両は、乗客が不安を抱いた瞬間に説明が必要になる。乗車前の同意、問い合わせ対応、遠隔の見守り。それを誰が担うかが曖昧だと、現場は動けない。もし運行開始が遅れれば、自治体や交通事業者との約束は先延ばしになり、現場の熱は冷える。同時に、電動化やソフト開発など他の投資案件との比較で、延びた時間はコストとして積み上がる。つまり、計画の敵は“技術の遅れ”ではなく、“前提が崩れる瞬間の連鎖”だった。
どうやって解決しようとしたのか
—ここから先は会員限定です—
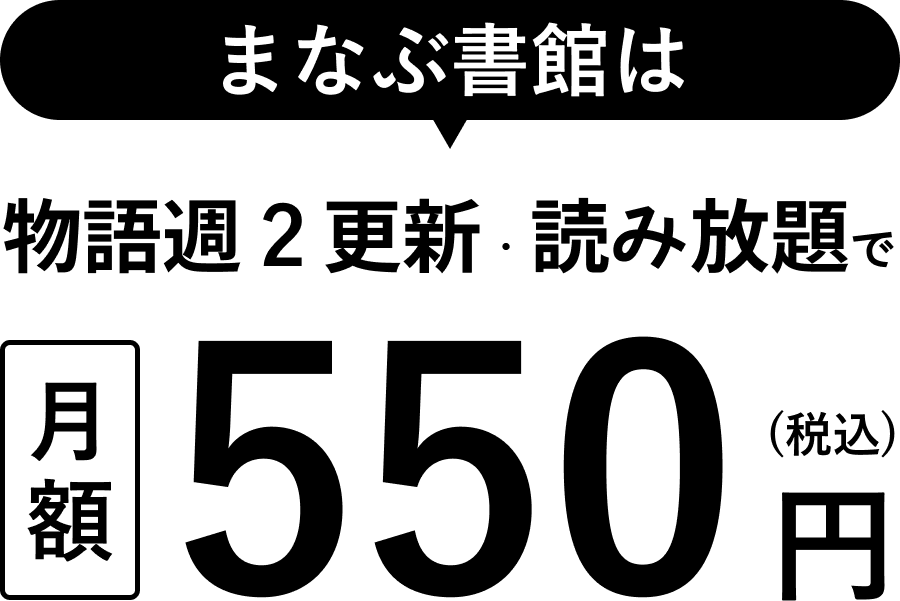
会員登録済みの方はこちら