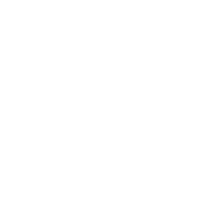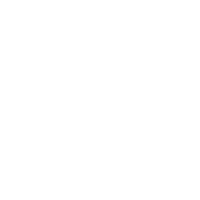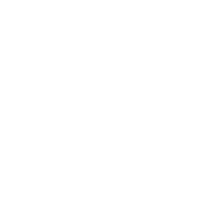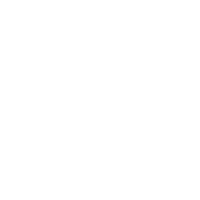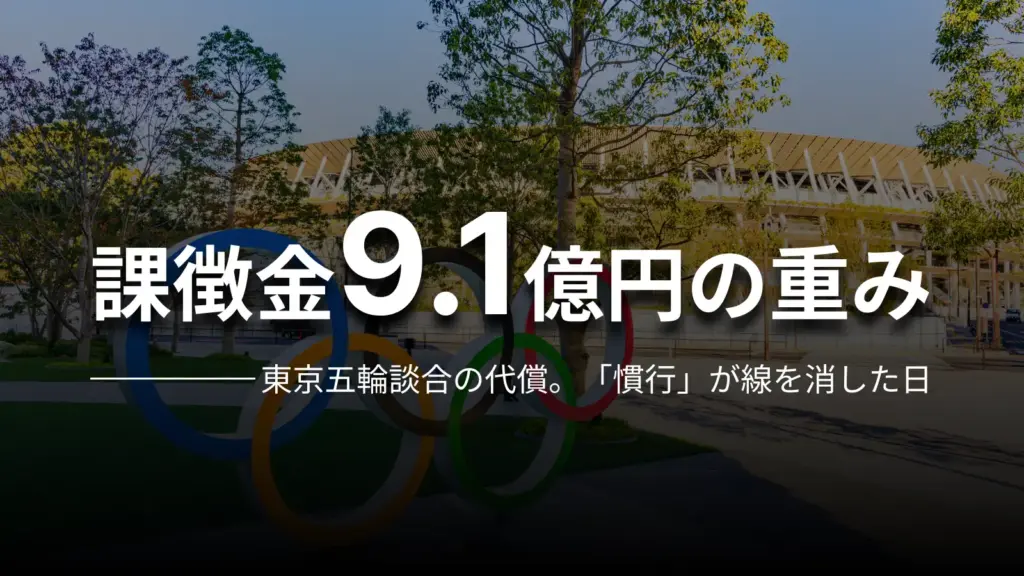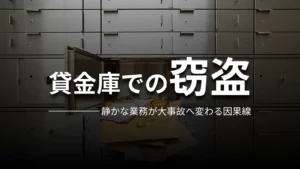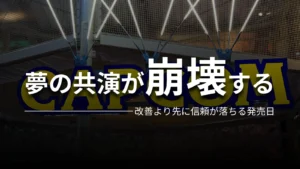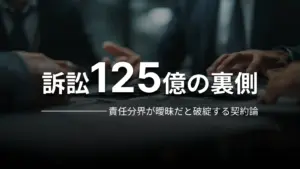罰金50万円が告げた夜、沈黙の残業が信頼を壊しきるまでの記録

夜のオフィスは静かだった。明かりが落ちても、仕事は終わらない。終電を逃した人の足音だけが、会社の鼓動のように響く。広告の締切は待ってくれず、修正は深夜に積み上がる。「あと少し」を繰り返すうち、記録に残らない時間が増えていく。それでも会社は回ってしまう。だから危機は、炎ではなく霧のように広がった。やがて、その霧は一つの報せで断ち切られる。違法な長時間労働――そして、裁判所の罰金。数字は小さく見えても、意味は重い。現場の背中に、説明できない重さが乗る。誰のために、何を守ろうとして、止める決断が遅れたのか。最も痛かったのは、崩れたのが売上ではなく“信用の前提”だったことだ。[1]
この物語の主役となる企業はどこか
これは、株式会社電通の物語。企業や社会の課題を言葉と映像に変え、商品やサービスの選ばれ方を設計してきた。多数のクライアントと媒体、制作会社、そして自社の専門職がつながり、成果は一人では完結しない。会議の結論は、そのまま翌朝の素材や出稿に直結する。だから調整は複雑で、締切は短い。2015年12月25日、若手社員の死をきっかけに、働き方の歪みが表に出た。東京労働局の立ち入り調査、全館消灯などの緊急措置、家宅捜索を経て、法人として書類送検される。そして2017年、東京簡易裁判所が罰金50万円の有罪判決を言い渡した。広告という“前向きな未来”を描く仕事が、足元の時間を守れない矛盾を抱えていた。[1][2]
- 自己申告では漏れる労働時間を、PCログ等の客観データと運用ルールで補完し、例外処理も定義し小さく始めて拡張する考え方
- 「再発防止」を口約束にしない、責任者・期限・検証指標を先に置き、進捗を公開し外部の目も借りる対話の作り方
- 法令対応をコストで終わらせず、信頼回復の設計として、次の仕事を取り戻すまで説明する実務にする技術手順
どんな問題に直面していたのか
問題は、突然の事故ではなく、積み重ねの習慣だった。新入社員は試用期間が終わると業務量が急激に増え、周囲は「助けたい」と「締切に間に合わせたい」の間で揺れる。業務のピークは予測しにくく、顧客側の意思決定や外部制作の遅れが、そのまま深夜の手戻りになる。一方で、労働時間の管理は、本人申告や慣行に頼るほど漏れが生まれやすい。“頑張った証拠”のつもりで隠れた残業が増えれば、会社はリスクを測れない。それでも現場は結果を出してしまう。成果が出るほど、長時間労働は“例外”ではなく“前提”へ寄っていく。2015年12月25日、若手社員が亡くなり、2016年9月に労災認定、10月には東京労働局が本社へ立ち入り調査を行った。全館消灯などの緊急措置が取られる一方、11月には家宅捜索が入り、組織の問題は公の場で検証されることになる。そして書類送検へ向かう流れの中で、会社は「現場の善意」に頼った経営の危うさを突きつけられた。社会全体でも長時間労働の削減は重要課題として位置づけられていた。にもかかわらず、組織は「止める」より「回す」を選びやすい構造にいた。[1][4]
どうやって解決しようとしたのか
—ここから先は会員限定です—
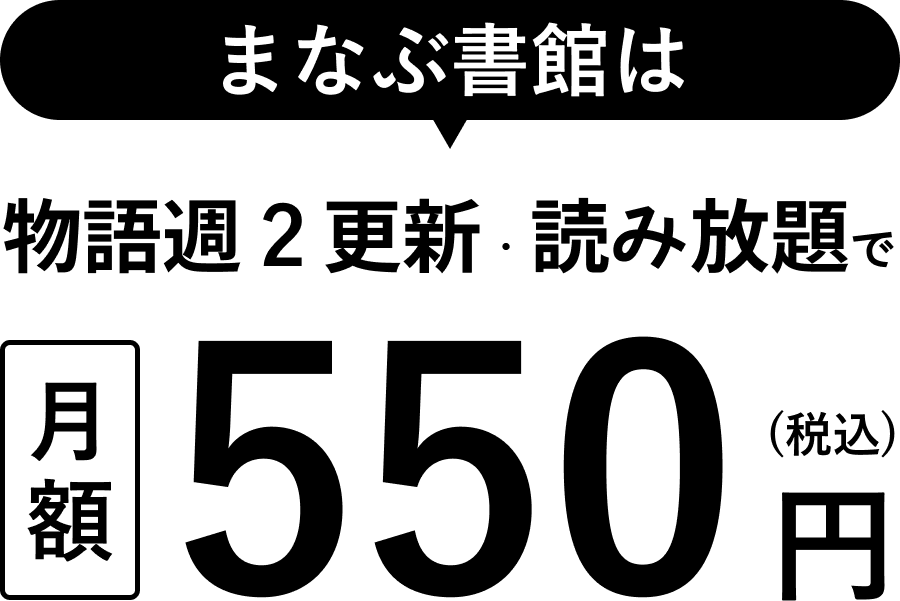
会員登録済みの方はこちら